初めの一歩は「日常」から

※筋肉・神経・身体についての記述は全て「トシオとイクミの俊カイロプラクティック院」の理論となります。
専門家を活用する前に

何事においても1歩1歩の前進が大切です。「足元からの積み重ね」がお子さんの身体を変えていきます。そりゃもう「改革」レベルで。
「自分は素人だから習い事で」とお考えの保護者さんも多いですが、実は「土台を整える環境」は習い事の練習より「日常生活」の中に潜んでいます。
- ちょっとしたことを知っている
- ちょっとしたことに取り組む
- ちょっとした1手間を惜しまない
生活にほんの少しの変化を投げ込むだけでお子さんの身体には小さな種が撒かれます。
是非、お子さんの日常を通して「種」を撒いてあげて下さい。その種が何処で芽吹くかはわかりませんが、撒いたからこそ芽吹くのです。
先生なら日常に沢山ある
日常生活に溢れる「2軸の先生」。それは何か道具を使ったりする必要はありません。
親がストップウォッチ片手にしっかり付添いが必要な「練習」ではありません。

先を急がず、初めの一歩から取り組めば良いのです。
そして、その方法は実は「足元」に転がっているものです。
親子で一緒に取り組んでみてください。お子さんが一人で取り組むのは「練習」ですが、親子で一緒に取り組むと「レクレーション」へと変わります。
1.階段は踵までしっかり
まず、エスカレーターを止めましょう。エレベーターも止めましょう。そして階段を「踵までしっかりつけて」上がっていく習慣をつけてください。
これが2軸の入り口となります。
※他の人の階段動作を見てみましょう。殆どの人が「爪先」で登っているはずです。

こんな感じ。踵が浮いている。
この階段の登り方が「楽」だと感じている限り、1軸運動+O脚+骨盤後傾の無限ループにはまります。※日本人男性に非常に多いです。
2.坂道を沢山歩こう
坂道を沢山子供と一緒に歩いてください。走るのも良いです。傾斜のある道を歩く・走る程に平坦な道では中々動き出さない「お尻の筋肉」がしっかり働く様になります。

お尻は坂道でやっと働き出す
これも2軸運動への布石となります。
3.子供と度胸試しをしよう
「気を付け」の姿勢からまっすぐ前に倒れ込む「度胸試し」を楽しみましょう。親が前でしっかり受け止めてあげれば大丈夫です。段々と支える位置を地面に近づけて「倒れ込む感覚」を根付かせてあげましょう。

脚は地面につけて大丈夫です。受け止めるのが大変になるので
これもまた立派な2軸運動への種蒔きです。
草履を履く
別に草履じゃなくてもいいんですけど、一番身近で経済的で確実な履物が草履だったもので。
学生アスリートであれば足袋シューズの「きね屋無敵」が断然おススメです。履いた瞬間に違いを感じ取れると思います。
- 親指をしっかり使って歩く・走る事
- ソールの力を借りずに自分だけで動く事。
たったこれだけでも2軸運動の基礎固めになります。

2軸は昔の履物に限る
工夫次第で幾らでもある
子供に2軸運動の種を撒く日常はまだまだ沢山あります。ですが、まずは上記3つを取り組んでみましょう。それができないと次に進めません。
日本人の悪いところは「先を急ぎ過ぎる」所です。足元を大切にして1歩1歩確実に前に進む事をおススメします。

〇2軸の種蒔きは日常から
〇親の覚悟一つで楽しくできる
階段から始める2軸歩行
爪先で歩く人が殆ど。むしろ階段を使わない人が殆ど。これでは1軸重心、後ろ重心の練習をしている様なもの。O脚を自ら作り出している状態と言えます。
そこで「階段をしっかり踵をつけて上がる」事から始めましょう。
重心が前に変わり、しっかりお尻と股関節が運動に参加する感覚を掴んでみよう。それが2軸歩行の第一歩です。
エレベーターを止める。エスカレーターを止める。
階段を踵をしっかり使って上がる。
たったこれだけの「日常の変化」であなたの二軸運動の基礎は間違いなく積み重なっていく。
2軸運動の指導をしている身で言うのもなんだが「教室で2軸運動の練習をするより効果的」と言える。
坂道を使ってお尻の感覚を
万博外周や健都周辺の線路沿い等、歩くに困らない千里丘周辺ですが「坂道」を上手に使うともっと良いです。
現代社会はお尻の筋肉を使う事が少なく、どんどん太腿中心の運動リズムが定着しています。
坂道を使うだけで「お尻」の運動参加が増加します。
2軸運動には「お尻の筋肉」が運動参加するのは最低限の要素です。
2軸動作を学びたいならお気軽にどうぞ!
千里丘駅西口から徒歩5分、産業道路沿いにあるトシオとイクミの俊カイロプラクティック院では大人・子供問わず「2軸動作」を学ぶ「からだの学校」を開催しています。
北摂地域で専門的に2軸動作を学べるのは当院だけ(のはず)なので、身体をもっと使いこなしたい、自分の限界を突破したいという方はお気軽にご相談下さい。
- >>メールのお問い合わせ
- >>LINEでのお問い合わせ
- >>電話でのお問い合わせ
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
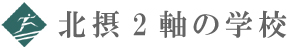



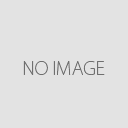









この記事へのコメントはありません。