こうして「2軸歩行」に辿り着いた
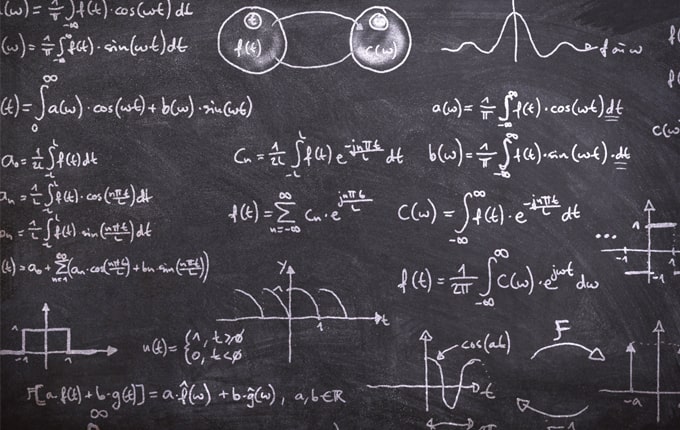
※筋肉・神経・身体についての記述は全て「トシオとイクミの俊カイロプラクティック院」の理論となります。
こうして2軸に辿り着いた

2軸物語(序章):よし、歩行を極めよう
全ての始まりは「歩行を極める」という目的です。
「歩行とは何ぞや?」
歩行分析の専門書を5~6冊買いこんで読んだら「全部、内容が違っていた」という衝撃。
正しい歩行って誰に聞けばいいんだろう。そんなシンプルな問いが浮かんだ時に思いついたのです。

専門書を全て読んでもどうしても納得がいかない。実際の感覚とデータがどうしても一致しない。
じゃあ、自分の感覚に従って考えてみよう。
まずはやってみよう。そこから始まったのです。
2軸物語(2):あれ?本と違うぞ
毎日2~3万歩を歩行に費やす日々が始まりました。そりゃもう色んな事をしました。
- 靴を色んなパターンに履き替えて変化を見る
- 靴下を色んなパターンに履き替えて変化を見る
- ノルディックウォーキングを導入してみる
- 道の起伏ごとの変化を感じ取ってみる
- 心拍計を導入して調べてみた。
- 歩き方そのものを研究する
ここで気付いた事がありました。

歩き方・道・靴・道具・ペース、それぞれの違いで歩行が微妙に変わってくる。
特に「靴」による変化は凄まじかった。テクノロジーの恩恵といったらそれまでだけど、歩行動作がもう「自分の物」ではなくなる感覚。
もう本に書いている筋電図なんて全くアテにならん。あれはどんな条件で抽出したんだろうか。平坦なエルゴを使ったんじゃないの?

こりゃ長い旅になりそうだと覚悟を決めた瞬間でした。
2軸物語(3):歩くと走るって同じじゃないの?
歩行分析を始めて早数年。歩行のメカニズム自体は大分理解できた感じになりました。
でもまだ納得がいかないポイントがある。

走る時は全身がバネの様に跳ね、地球上を飛び跳ねる様に進んでいきます。勢いがつきすぎて止まるのが大変なくらいです。急に止まると腰を痛めそう。
でも歩く時は速度が足りない分、しっかり地面を踏み込む形になってしまう。
「歩く」と「走る」がどうしても別運動の様になってしまいます。

どうしても「歩く」と「走る」が1本の線上に繋がらない。あからさまに稼働している筋肉が異なっているのです。
この差は一体何なんだ?
「走る」の手応えは十分感じている。となると「歩く」方で何か勘違いをしているのか。
更に歩行を追求する日々が続きました。
2軸物語(4):大殿筋は何をしている?
人間が2足歩行をする上で獲得した幾つかの強大な筋肉。その一つが「大殿筋」です。
でも、歩行の時はそんなに活躍しない。走る時は瞬間的に凄い活躍する。階段や坂道の時にも活躍する。
でも、歩行の際はほんの一瞬です。足が地面に接した瞬間にキュッと引き締まって終わり。

大殿筋の歩行における役割がどうしても腑に落ちない。4足から2足へ移行して手に入れた筋肉だ、絶対に深く関わっているはず。
「歩行」における最後の1ピースを埋める旅が始まった。
この時点で既に7年が経過していた。
2軸物語(5):あ、そういう事か
それはその時、その瞬間にやってきた。

最後の1ピース、大殿筋がどんな役割を担っているのか。腑に落ちたのだ。
- 大腿四頭筋
- 下腿三頭筋
- ハムストリングス
- 腹筋群
- 肩甲骨
- 広背筋
- 大円筋
- 小円筋
- 棘下筋
- 肩甲下筋
- 前鋸筋
- 菱形筋
- 脊柱起立筋
- 上腕二頭筋
- 上腕骨
- 大腰筋
- 大殿筋
思えば遠くへ来たもんだ。でも、7年目にしてやっとこさ全ての筋肉が1つのユニットとしてまとまった。全てに合点がいく。
何よりの大発見は。。。。

そう、遂に「歩く」と「走る」が同一線上に繋がったのだ。
ルフィより先に見つけたよ!ONEピース!
遂に1本の線上に繋がった「歩く」と「走る」の動作。生き物としてこれが最もシンプルで自然な形じゃないのか?
正解かどうかはわからない。でも、臨床家として納得がいくものができあがった。
ただ!ただ1つだけ懸念が残った。

真っすぐ歩くのが理想なんだ!と教え込まれた自分にはどうしても気になる点だった。
これは正しいのだろうかと。
機能性は完璧に近い。でも左右に触れるという事は不安定なのか?当事者としてはド安定なんだが。。。
2軸物語(終章):あ、2軸ってピッタリじゃん
安定は十分、推進力も十分。でも左右に揺れてしまう。さぁどうしよう。これは「正解」と言っていいのだろうか。
今まで見てきた「正しい歩行」は大抵が似たような事を言っていた。
- 頭の位置が変わらない
- 肩が揺れない
- 重心位置が微動だにしない
自分が辿り着いた理想形はそのいずれにも全く当てはまらないのだ。

自分は歩行の権威ではない、やっぱり自分のは間違っているのか?
歩く度に「いや、これだと思うんだけどなぁ」と思いながら「でも、歩行の専門家が言うにはなぁ」と悩みつつ半年くらいが過ぎた頃。
「2軸動作」という言葉を見つけたのである。
陸上関係の本を見ていた時だったと思う。かなり有名な人が書いた本みたいだった。
そこで歩行動作について書いていたのだが、私は衝撃を受けた。

歩行動作で必ず起こる自然現象「自然落下」を無視して持論を展開していたのだ。
権威ある第一人者でもこんなものなのか。そう衝撃を受けてすぐ思った。

その本を更に読み進めていくと出てくるのが「2軸動作」について。

自分が辿り着いた歩行動作と「かなり近い事」を提唱していたのだ。
そうか、自分が辿り着いた理論は「2軸動作」という言葉で昔からあったのか。知らなかった。
ちょっと自分の2軸動作とは違うが、説明するのに「2軸動作」はとても便利な言葉だ。

そうして「北摂2軸の学校」が生まれたのである。
2軸動作を学びたいならお気軽にどうぞ!
千里丘駅西口から徒歩5分、産業道路沿いにあるトシオとイクミの俊カイロプラクティック院では大人・子供問わず「2軸動作」を学ぶ「からだの学校」を開催しています。
北摂地域で専門的に2軸動作を学べるのは当院だけ(のはず)なので、身体をもっと使いこなしたい、自分の限界を突破したいという方はお気軽にご相談下さい。
- >>メールのお問い合わせ
- >>LINEでのお問い合わせ
- >>電話でのお問い合わせ
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
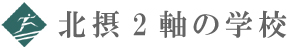





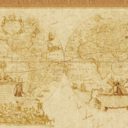

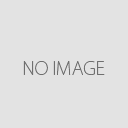




この記事へのコメントはありません。