悲劇の筋肉:腸腰筋

※筋肉・神経・身体についての記述は全て「トシオとイクミの俊カイロプラクティック院」の理論となります。
誤解を受けた腸腰筋

本来、鍛えるべき筋肉ではない
腸腰筋という筋肉があります。サッカー選手の長友選手が本を出版されて認知が爆発的に広がりました。
「体幹筋」という表現の方が一般的かも。
この本が出てから一気に学生アスリートが傾きだしました。腸腰筋強化へ。

こんな感じです。
その結果、安定を手にした代わりに機動性を失った学生アスリートが爆発的に増えたのです。
腸腰筋は鍛える筋肉じゃない

そもそも論なのですが、腸腰筋は「鍛える筋肉」ではありません。インナーマッスルなので「微調整筋」です。鍛えるならアウターマッスルで随意筋である腹直筋や腹斜筋の方が圧倒的に優先順位は高いのです。
バランスの取れた筋肉、そして神経促通ができていれば腸腰筋は勝手に太くなっていきます。何故なら「運動参加」するからです。
太くする筋肉ではないのです。
太くなる筋肉なのです。
腸腰筋の抱える問題は「緊張」
実は腸腰筋が抱えている問題は「細い」ではありません。「緊張しっぱなし」になっている事です。
これは腹筋不足やお尻の殿筋不足が生み出す後方重心によるものです。日本人にとても多い。その為、体幹の安定を失い腸腰筋が代償性でカバーするしかなくなっています。これが問題なのです。
野球でいうなら監督がマウンドに立っている状態です。
腸腰筋は鍛えるべき筋肉ではなく「本来の仕事に戻す」べき筋肉なのです。
一刻も早くベンチに下がったスタメン(アウターマッスル)をグラウンドに戻してあげましょう。
ひょっとするとひょっとする
長友選手は体幹筋を鍛える、というテーマで書籍を出していましたので「腸腰筋」「体幹筋」を鍛えるという事を謳っていたかもしれませんが、実際のアスリートは「勝手に太くなっていた」というケースが殆どです。ひょっとしたら長友選手の場合も「結果的に大腰筋が太くなってたみたい」という事だったのかもしれません。メディアの世界ではよくある話です。
少なくともオリンピッククラスの陸上選手は「腸腰筋」をターゲットにトレーニングをする事はありません。皆、結果的に腸腰筋が太くなるのです。
腸腰筋カチカチが増えた
腸腰筋は確かに太くなる。でもそれは「アウターマッスル」が使いこなせた結果、インナーマッスルも積極的に運動に参加し始め、腸腰筋が使いこなされ太くなっていくというものです。決して「狙って鍛える」ものではありません。
そこの誤解が解けないまま話は進みました。
- 長友選手はこんなに偉大な選手だ
- 長友選手の大腰筋はこんなに太い
- という事は、大腰筋は凄い力を持っているんだ
こんな3段階活用が世の中に広まり、テレビ、雑誌、書籍には「腸腰筋が大切」という紋切型の専門家が大量生産されました。
そして、それを信じて「腸腰筋を鍛えればパフォーマンスが上がる」と信じた学生アスリートがこぞって腸腰筋の筋トレを開始。アウターマッスルが不十分なままインナーマッスルである腸腰筋が無理を強いられる状況が増えたのです。

全国各地で「監督がマウンドに上がる」という不自然な状況が生まれました。※あくまで身体の中
その結果、安定感が増した一方で機動性を失った学生アスリートが全国各地に溢れました。全国区の選手ですらそうです。むしろ全国区の選手の方に多かったと思います。何せ彼らは時代の最先端を追っていますから。
筋肉を知っていれば防げた悲劇
この腸腰筋の悲劇は筋肉について予め知識があれば防げた悲劇です。

腸腰筋が太いのはわかるぞ!

でも、腸腰筋を鍛えるは違うんじゃない?

腸腰筋って柔軟性が大事じゃん
つまり、腸腰筋は「鍛える筋肉」ではなく「使う事で磨かれる筋肉」であると知っていれば「鍛える」行為に違和感を感じ取れたはずなのです。
但し、腸腰筋に関しては専門家すら間違った認識でいる場合も多いので中々難しいところです。
膝上げを例にする
例えば立った姿勢で膝を持ち上げる運動。それを「腸腰筋が主導筋となる運動だ」とする専門家が沢山います。
ですが、それは「膝を持ち上げる」という行為単体においてです。
実際の重力下では膝を持ち上げる為に身体を安定させなくてはいけませんが、その為にはまず背筋群と腹筋群による胸郭と骨盤の安定性の確保が必要となります。その土台が確保された時点で初めて腸腰筋が大腿筋膜張筋や大腿四頭筋その他の筋肉の助けを借りて足を持ち上げるのです。
腸腰筋は最後の方に動き出す「神輿に担がれた監督」みたいなものなのです。
〇腸腰筋は太くするではなく、太くなる。
〇「アウター筋」の腹筋群を鍛えよう
2軸動作を学びたいならお気軽にどうぞ!
千里丘駅西口から徒歩5分、産業道路沿いにあるトシオとイクミの俊カイロプラクティック院では大人・子供問わず「2軸動作」を学ぶ「北摂北摂2軸の学校」を開催しています。
北摂地域で専門的に2軸動作を学べるのは当院だけ(のはず)なので、身体をもっと使いこなしたい、自分の限界を突破したいという方はお気軽にご相談下さい。
- >>メールのお問い合わせ
- >>LINEでのお問い合わせ
- >>電話でのお問い合わせ
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
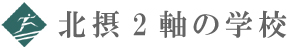




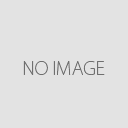







この記事へのコメントはありません。